

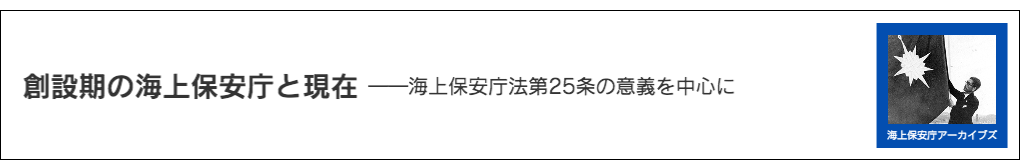
第1回(全3回)
海上保安庁は軍隊ではない
海上保安庁法(以下、「庁法」と略すことがある)は1948(昭和23)年に制定された。その第25条は「この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない」であり、現在まで改正されることなく存続している。制定当時、第25条は国際的にも国内的にも重要な意義をもっていたが、その後、これは念のための規定であり、あってもなくてもさほど重要なことではない、という認識がもたれた時期もあった。
しかし、海上保安庁は、その技術・能力を蓄積し、世界の先端を行くまでに成長してきた。海難救助、油汚染の防除、海賊対策など、近隣諸国の海上保安機関との連携・協働の重要性を、経験的にも認識してきた。そして、尖閣諸島の警備が国の最重要な問題の1つとなり、さらに、21世紀を迎えた、平時における世界の海洋秩序の維持は、国連海洋法条約にもとづく、世界共通であるはずの国際法に根拠をもち、国際法と整合した国内法にも確固たる根拠をもつ、海上法執行機関の連携・協働により達成されるべきものとの理解が、世界常識となってきた。
わが海上保安庁が、積極的に近隣諸国の海上保安機関の設立に協力し、既成の海上保安機関に対しても、国際法の知識、法執行技術、海難救助技術の指導、移転、そして状況によっては巡視船艇の供与なども含む各種技術やノウハウの教育、移転といった活動をすることにより、連帯した活動による海洋の秩序維持がなされるべきことが重要と認識され、現在に至っている。
その根底にある考え方は、軍事組織ではない、海上における法執行機関、すなわち警察機関によって、国際政治や軍事的対立とは一線を画した、つまり、そのような政治的、軍事的影響を受けずに、海洋の安全・秩序を維持することが、世界平和にとっても重要であるという認識である。そのことが、普通の(まともな)国々に理解・支持され、法治・平安の海の実現が達成されつつあり、また達成されなければならないと考えられている。
しかし、最近、北朝鮮をめぐる危機的状況、尖閣の緊迫した状況を踏まえてのことと考えられるが、庁法第25条の存在が、海上自衛隊と海上保安庁(以下、「海自」「海保」と略すことがある)とのスムーズな連携を阻害しているとか、庁法第25条を削除し、海保をより軍隊なみに強化し、ことに当たらせるべきではないか、といった議論があると仄聞する。そこで、海上保安庁の創設、中でも庁法第25条が規定された経緯と、その現代的意義について改めて考察してみたい。
さて、わが国では、海自と海保とでは、その任務、機能、性質などは根本的なところで明確に分かれており、いわゆる「軍警分離」が確立しているといってよい。先進民主主義国では(全部ではないが)軍と警察の機能は明確に分離されており、平時の治安維持(デモの警備などに)に軍隊を使用することが禁止されるのが原則である。陸でおこなわれてきた軍隊と警察との任務・機能の分離、すなわち軍警分離は、海上でも進んできており、21世紀を迎えた海上の安全確保、治安の維持についても重要な意義をもつようになっている。
そこでまず、海上保安庁が創設された経緯の中でなぜ25条が規定されたかという理由、時代背景について、若干の歴史を顧みながら、考察し、ついで、海上保安庁法25条の現代的意義と、国連海洋法条約の時代である現在の海洋の秩序維持に関係して、この25条があるゆえの状況や意義などについて、考察してみたい。
終戦直後の日本を取り巻く海の状況と
海上保安庁の創設
1945(昭和20)年8月15日に先の大戦は終わり、海軍は解体され、日本周辺の海域に力の空白が生じることとなった。『海上保安庁十年史』はつぎのように記している。
終戦当時わが国周辺の海域は、悪質犯罪の跳りょうする舞台と化した。それは国内のやみ取引を助成する大動脈であり、密漁者の黄金の漁場であり、密貿易と不法入国のために開放された門戸であった。船内と博の如き刑法犯も盛んに行なわれ、海賊の横行さえしばしば伝えられた。一方、船舶航行の安全についても終戦当時ほど不安と危険にさらされた時代はなかった。元来、1万海里にもおよぶわが国の沿岸水域は、複雑な海岸線と気象海象の急激な変化によって世界屈指の海難多発海域とされているが、海上保安機能に加えられた戦争の打撃はまさに致命的であった。航路標識の壊滅、水路測量能力の低下、船舶の構造及び設備の劣悪化、優秀船員のそう失等によって、航海の安全を保つために必要な基礎はすべて失われ、海事諸法令の大半は死文と化した。そのうえ日本が敷設した係留機雷55,347個、米国のB29及び潜水艦が敷設した感応機雷10,703個が日本近海の水路や主要港湾を覆い、多数の沈船や密航者が放棄した船舶とともに船舶の航行をおびやかしていたのである。
このように、海上の治安および航行の安全は、終戦直後著しく不安と危険にさらされ、まさに暗黒の海を現出していたが、この事態に対処すべき国家機関はあまりにも微力であった。戦前には治安の維持については水上警察、税関、海運局などの諸機関が、それぞれの主管に属する法令の励行に当たってきたが、いずれも実力強制の力が弱かったので、取締上の最後の実力行使の面は、すべて海軍に依存してその目的を達していたのが現実であった。
そのため、終戦による海軍の解体によって日本の海上保安機能は弱体化してしまい、この空白状態を満たし、明るい海を建設することは、わが国の政府にとっても、日本を占領している連合軍にとっても重要な関心事であったのである。
加えて1946(昭和21)年初夏、朝鮮で「コレラ」が蔓延し、不法入国船を介してその恐るべき病毒が日本に侵入し流行する徴候が発生し、悪疫の侵入を極度に恐れた連合軍当局の指令で、日本政府は、海運総局に不法入国船監視本部を置き、九州海運局に不法入国船監視部を置いて、密航船の監視取締りをおこなった。コレラが海保の創設を促した要因の1つといわれるゆえんである。このような事態は、取締りの必要性、海上警察力の必要性を要求することになるのであるが、当然のことながら、当時の海運総局に、軍事的思考、意図など微塵もないことは明らかであったと思われる。
このような情勢下、1946(昭和21)年3月、わが国の海上保安制度を調査し、対応策を樹立するため、アメリカ合衆国コーストガードのフランク・E・ミールズ大佐が、連合軍最高司令部(GHQ)の要請により来日し、海上保安の一元的な管理機関設置の必要性を特に強調した助言と勧告をおこなった。
この点に関して、大久保武雄初代海上保安庁長官の『海鳴りの日々―かくされた戦後史の断層』(1978(昭和53)年6月1日、海洋問題研究会)から引用させていただく。
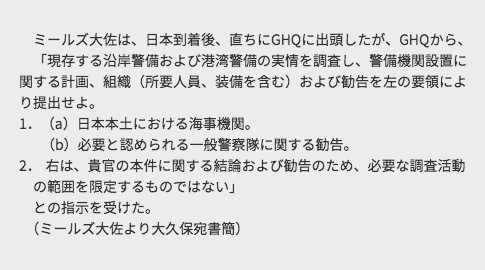
大佐は、綿密に日本の習慣や伝統を研究するかたわら、海上の治安警備の実状を視察して、1946(昭和21)年7月、マッカーサー総司令官に、「GHQから運輸省海運総局に水上保安組織を作るよう指令すべき旨」勧告し、「水上警察の機能は海運総局に移すこと、水上保安組織は人命救助を重要任務としているので、それに適した監視船を用意すること」を提言した。このミールズ大佐の勧告で日本政府内の所管争いは決着がつき、運輸省を中心として準備を進めることとなった。
またミールズ大佐は日本政府に対し、「GHQでは日本の軍備再建を非常に警戒しているので、これを刺激するような案は作らない方が賢明だ」とまで注意してくれた。これは、ホイットニー、ケーディス等GHQ民生局主脳の意向を暗に知らしてくれたものであった。ミールズ大佐の勧告を、夜明け前にときを告げる一番鶏の声のように、私たちは聞いた。
この勧告がなされた経緯からも、当時の占領政策の厳しさからも、GHQは海上警察機関が必要だと考えたのであって、軍事機関を創設する意図など全くなかったことが窺われる。同時に、勧告を実行に移そうとする日本政府にも、ましてや海運総局にも、海軍の復活(再軍備)の発想など微塵もなかったことは明確であると断定できる。
そして日本側としては、1947(昭和22)年5月22日の次官会議において、運輸省に海上保安機関を設置する案を正式に採用し、政府は閣議了解後、GHQに対して海上保安機関設置の許可を申請したのである。